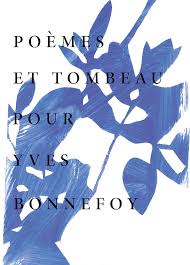
フランス現代詩研究会 2020 年 6 月例会
- 日時:2020 年 6 月 26 日(日本時間 20:00-23:00/フランス時間 13:00-16:00)
- 場所:日本/フランス(オンライン)
【ワークショップ(読書会)】
-
発表者:関大聡
-
対象詩:Michel Deguy, Poèmes et tombeau pour Yves Bonnefoy, La Robe noire, 2018.
- La ballade des mourants
- Adieu, donc Joachim
- Préparatifs pour un tombeau d’Yves Bonnefoy ([Dans la nuit…], [Les larmes attestent…], [Présence ?])
【報告】読書会を終えて(森田)
ミシェル・ドゥギー(1930-)は 2020 年現在、90 歳の誕生日を迎えた今も精力的に詩を書き続けています。この会ではおよそ 6 年振りにミシェル・ドゥギーを取り上げましたが、今回は 2018 年に出版された最近の詩集から数篇の詩を、およそ 10 名ほどの参加者で読むことになりました。はじめに関さんの方から、ドゥギーにおける哲学的背景(ハイデガーをはじめとする「住まうこと」をめぐる問題系)を、近年のドゥギーが取り組んでいる地球環境問題に対する政治的参加(アンガジュマン)との関連から解説していただきました。一般に難解と知られているドゥギーの詩でしたが、関さんの解説や、詩に登場する固有名詞や哲学的な概念などを皆で調べながら読み進めていくうちに、徐々に語られる詩人の姿を浮かび上がらせていくことが出来たように思います。現代西洋社会における移民との共生の問題を憂いたり、愛すべき存在が出生する一瞬に儚い期待を抱いたり、はたまた、死者への追悼を想う中で自身の中にある死と向き合う姿を見つめたり… これらに共通するのは、どれもが切実な思いで発せられているという点で、切迫感のあるものだったということです。彼の詩は、こうした差し迫る緊張感と、それを解きほぐす言葉遊びやアイロニー、過去の詩のパスティーシュといった知的な愉しみが同居しており、それが彼独特の世界観を構成しているように見えました。
読書 1:« Présence ? » (Préparatifs pour un tombeau d’Yves Bonnefoy)
この詩集の題名にも含まれているイヴ・ボヌフォワ(1923-2016 年)について書かれた詩を取り上げるにあたり、ボヌフォワ研究者の久保田悠介さんから、ドゥギーとの関係を紹介していただきました。最初に読んだ「現前?」(Présence ?)と題されたこの詩は、明らかにボヌフォワの現前(présence)をめぐる思想が背景にあるように思われます)。ボヌフォワにおける〈現前〉とは、一般的に「概念=本質を拒否して、可感の世界、存在するもの=現存[現前]への接近を詩に求めようとする」ものとして理解されているものです 1。この詩でも、〈現前〉を「存在、より『具体的には』、大切な存在がふと訪れ、現れる」可感的なものであるとしつつ、それがつねに「消滅の危機に晒されている」と言います。ここで気が付くのは、ボヌフォワにとっての「現前」が「現れる」ことが問題となる場合が多いのに対し、この詩では「消え去る瞬間」の方に重点が置かれているように見えることです。すなわち「愛する存在の消滅」、「『私』自らの『遺言なき』消滅」、「生を忘却させる微睡の介助者」といった〈死〉が、〈現前〉という一瞬と常に共にあるということでもあります。
〈現前〉はいつか死すべき運命にあります。ですが、〈現前〉が別の〈現前〉を作り出すとしたら、どうなるでしょうか。「誕生の瞬間は復活である」から始まる二連目では、ハンナ・アーレントの「新生」が引用され、複数の〈現前〉(Présences)への可能性が語られています。人間が生まれることで、世界をやり直して、新しい世界を作り出す期待が込められています。これらの「新生児たち」を「言葉に導いていく」べきであるというのは、この複数の〈現前〉を詩作品として描き出すことを言っているようにも思えます。一連目の単数形の現前のときとは異なり、二連目の複数形の現前は「会食者たちが互いに顔を見せ合うときに到来する」ものだと言われます。この会食は、アーレントが『過去と未来の間』で引用するルネ・シャールの詩からの連想という可能性が指摘されましたが、ここで新生というイメージを再び思い起こすならば、産まれた時に顔を見る親と新生児の関係にも比べられるかもしれません。最後のイタリックで書かれた一文「愛する存在であるより愛される存在であることで、魂の伴侶たちの連結符が始まる」は、まだ愛されることしかできない、誕生したばかりの新生児のことを指しているのではないかと思えました。
- 1. 久保田悠介「イヴ・ボヌフォワ:バロックとイマージュ」、『学習院大学人文科学論集』、26 号、2017 年、86 頁。 ↩