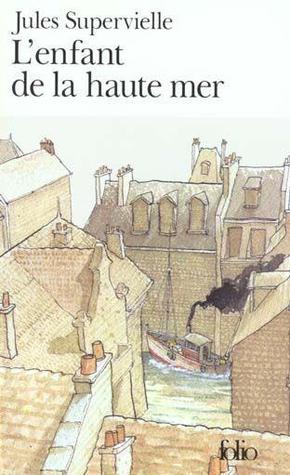
フランス現代詩研究会 2018 年 8 月例会
- 日時:2018 年 8 月 28 日(日本時間 21-24 時/フランス時間 14-17 時)
- 場所:東京/パリ(オンライン)
【研究発表】 「ジュール・シュペルヴィエルの conte-poème について」
- 発表者:佐藤園子(東京大学大学院博士課程)
要旨
シュペルヴィエルは詩作品同様、⻑編小説や戯曲、短編小説(conte)を残しているが、とりわけ詩と短編小説についてはその境界の相互浸透性を繰り返し述べている。実際に物語の形式は詩作品の中に組み込まれ、テクストを読者に伝える「導きの糸」(fil conducteur)の役割を負っている。他方で、シュペルヴィエルが「本当の短編小説はほとんど書いたことがない」「私のテクストのいくつかは、短編小説と詩の間にある」と述べているとおり、短編小説は詩的散文(prose poétique)、散文詩(poème en prose)に似通った様相を呈す。では、どのように韻文は散文に近づき、散文は韻文に近づくのだろうか。本発表では、詩篇 « 47 Boulevard Lannes » と短編小説 « Les boiteux du ciel »(あるいは詩篇 « Le Village sur le flot » と短編小説 « L’enfant de la haute mer » )を比べることでこの問いに応えることを試みたい。
【ワークショップ(読書会)】
- 対象詩:Le Corps tragique (1959) よりシュペルヴィエルが翻訳した作品 2 篇
- García Lorca « Le Martyre de Sainte Eulalie »
- Jorge Guillén « Les Airs »
参考 URL
報告
詩が持つイメージと散文が持つ論理が重なり合ったテクストは「詩」と呼ぶべきなのだろうか、それとも「散文」と呼ぶべきなのだろうか。佐藤園子氏の発表は、シュペルヴィエルの作品群に見られる、詩的なイメージと、その「詩」の中にある散文的要素が、縦糸と横糸のように重なりあっていく過程を、具体的な詩作品の読解を通じて示すものであった。
ここでの「散文的要素」とは、「論理」、より正確には「物語の論理」と言い換えることができる。それは、シュペルヴィエルによれば、彼の同時代人であったシュルレアリストたちにしばしば見受けられる、イメージ優位の作品群には欠けている要素でもあった。とはいえ、この散文的要素を強調することは、かえって詩が発するイメージの広がりを拘束してしまうことに他ならない。そこでシュペルヴィエルは、直線的な論理を展開しながら進む散文に対し、詩を「同心円を重ねて進むもの」として提示する。
このように、シュペルヴィエルの詩作品は、詩と散文双方の〈弁証法〉を目指したところに特性が認められる。より具体的には、詩の中に、散文的要素という「導きの糸」を用意することで、詩が持つイメージを読者にとって親しみやすいものとしているのがこの詩人の特徴である。ここで重要なのは、彼の言う導きの糸が、決して自作に解説を加えるものでも、解釈を固定させるような明確な答えを準備するものでもなく、あくまで「糸」というささやかな指針に他ならないということである。というのも、シュペルヴィエルは、詩が持つイメージを破壊することなく、「詩の中で起こりうる奇跡を奇跡として読者に届ける」ことを目指していたからである。シュペルヴィエルは「読者に理解されることに対するいわば強迫観念のようなものがあった」と佐藤氏は指摘するが、それは必ずしも詩を万人にわかりやすく説明するような「等身大の幻想」を目指すものではないだろう。
以上の詩的イメージと散文的論理の共存形態を示すため、佐藤氏は詩篇 « Bon voisinage » の詳細な分析を行った。以下にその読解の一部を取り上げる。この詩の前半では、「アルゼンチン」から「中国」に「一輪の薔薇」を投げる、という「奇跡」が、詩的イメージとして提示されている。ただし、それが何を意味するかまでは読者には提示されていない。しかし、後半部まで読み進め、再びこの「薔薇」という言葉が現れたとき、最初の奇跡のイメージが「遠く離れた二人の愛を可能にする」ものであることがわかる。一見すると、薔薇=愛という形式的図式によって読み終えてしまうことのできる詩にも見える。しかしここで佐藤氏は、問題の後半部に入る直前で、時制と語り手のアクロバティックな切り替えが生じていることに注意を向ける。というのも、この唐突な切り替え=切断は、前半部の薔薇の奇跡のイメージが、散文的論理とは別の時空間で生起していることを示すものだからである。つまり、この詩自体が、薔薇=愛という図式で読むことを促してはいないのである。この詩全体を薔薇=愛として読むか、「奇跡」の謎を抱え込んだままにするかの判断は、最終的には読者の手に委ねられているのである。
質疑応答では、シュペルヴィエルが詩と散文の融和とも言える状況を、あえて〈弁証法〉という哲学的(あるいはそれを介したシュールレアリスム的)な呼称を用いた理由についての質問が挙げられた。これに対し佐藤氏は、シュペルヴィエルの〈弁証法〉が、ポーランの手紙の中で部分的に用いられたものであり、なおかつ本人が「弁証法が詩的なものであるように努めている」と語っていたことからも、独自の解釈である可能性が高いとした。その他、詩作品の読解に関する質問が多く寄せられた。とりわけ興味深いものとして、詩篇の中盤における « Que les absents ne sont pas dans leur tort, »「いない人は間違っていないし」 が、« Les absents ont toujours tort »「いない者はいつも悪者」ということわざを裏返したものなのではないか、という指摘があった。
(報告者:森田俊吾)